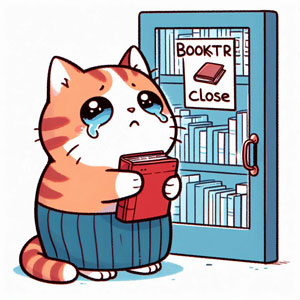大阪府中小企業診断協会からいろいろなイベント案内が届くのですが大概は無視。そこに日本酒試飲会という魅力的なお知らせが!
迷わず参加申込!申込した後によく見ると青年会のイベントです。さすがに青年じゃないなとキャンセルしようかなと、さらによく読むと診断協会の会員なら誰でも参加OKと書いてあったのでそのまま参加。青年会主催なので若い参加者ばかりかいなと思ったらいつもの酒好きのシニア層が集まっていました。人のことはいえませんが(笑)
ずっと試飲会と思って参加したら日本酒の講義からスタート。講師は浅野日本酒店の浅野社長です。中小企業診断士で梅田、京都、三宮、浜松町、横浜の5店舗を運営しています。オイオイ、飲み会じゃないのと思ったら、後半は試飲会で風の森や3年物の古酒などけっこういただきました。満足!満足!