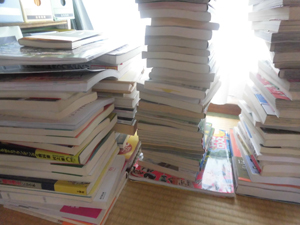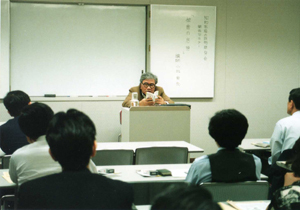知り合いの安田さんが毎年、カンボジアの子供たちに「自転車」を届ける活動をしています。
クラウドファンディングReady forを活用しているんですが、プロジェクトが無事に終了し、写真などの報告が届きました。今回提供された自転車が165台、3か所の新たな自転車クラブの設立、13か所の既存の自転車クラブへのパーツ補給ができたそうです。
カンボジアは中学が少ないため10キロ~20キロが校区になります。自転車が無いと徒歩で数時間かけての通学となります。農村地域ですので中学生の親は農業を営んでおり、中学生の子ども達は親にとっては貴重な労働力です。だから「学校なんて行ってる暇があったら農作業を手伝え!」となり学校に通うことを諦めてしまいます。
これでは貧困を抜け出せませんので、学校でたくさん勉強して自分の人生を切り開き、家庭を支えたいと考える子供たちに自転車を送り通学時間を少しでも短くなるよう安田さんが手助けしています。
自転車には協力者の名前入りパネルがつけられるので、今頃、「合同会社エムアイティエス(LLC MITS)」のパネルをつけた自転車がカンボジアを走っていることでしょう。