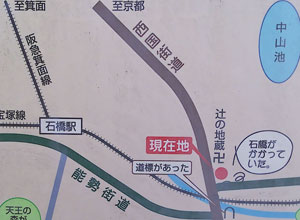山崎宿から東を目指します。まずは山崎の合戦跡。天正10年(1582年)6月2日に本能寺の変が発生し、6月13日に行われたのが山崎の合戦です。摂津から西国街道を進んできた秀吉軍と明智軍がぶつかります。天王山の戦いとも言いますが、実際に戦いの舞台になったのは山崎宿から少し東にいった小泉川になります。今は大山崎JCTがあります。
明智軍は川沿いに柵をもうけ長篠の戦いの再現を目指したという説もあります。戦いは雨が降る中、夕方にはじまったようで、最初は双方とも互角の戦いだったようです。秀吉側の池田恒興らが小泉川を渡り、明智軍の側面から攻撃したため浮足立った明智軍の雑兵が逃げ出し総崩れになります。