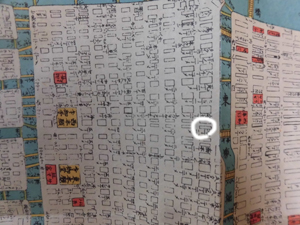竹取物語には藤原氏告発本という側面がありますが、同様に”おとぎ話”にはいろいろな側面があります。

桃太郎といえば鬼ケ島への鬼退治で有名ですが、一説には吉備津彦命による温羅退治伝説であると岡山では宣伝していますが諸説あります。
■吉備津彦命は奈良生まれ
孝霊天皇の皇子なので都があった黒田廬戸宮で生まれたといわれています。近鉄田原本線・黒田駅のすぐ近くです。吉備津彦命は四道将軍の1人となり、西道に派遣されます。
纏向遺跡の発掘で吉備が大和政権設立に貢献した強国ということが分かっていますが、どっかで方針があわなくなったのか吉備は政権に攻められる側となります。この時に吉備津彦命が派遣され温羅退治伝説になったと言われています。吉備津神社縁起物によれば犬飼という名前の部下がいたのと猿飼部、鳥飼部の一族を引き連れていたそうで、これが犬、猿、キジとなっていきます。ほんまかいなあ(笑)。