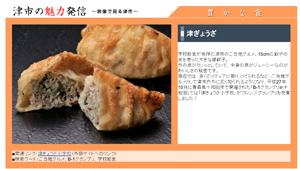楢原氏の菩提寺である九品寺は行基が開祖と伝わるお寺ですが、青森県から宮崎県まで行基が開基したとの伝承がある寺がなんと約600!。まあ聖徳太子伝説と同様にあやかってということでしょう。
岸和田にある久米田寺は正真正銘、行基が開祖となっています。行基が開祖した49院というのがあり、その中にある隆池院(久米多)が現在の久米田寺です。創建は738年と伝わっています。久米田寺の隣に久米田池という人工池(ため池)があり、聖武天皇の命をうけて行基が開削し、この久米田池を維持管理するために作られたのが久米田寺です。
戦国時代は三好実休と畠山高政が戦った久米田の戦いや織田信長による高屋城の戦いの兵火等により、寺はほぼ焼失しますが江戸時代に本堂などが再建されました。