
昔、高安駅近くに住んでいた頃、西部八尾に時たま行っておりました。2017年2月に閉店となりましたが、その後にできたのが「リノアス」という商業施設。
昨日、八尾へ行く機会があったので中に入ってみましたが、けっこう賑わっていました。隣にあるアリオ八尾への渡り廊下も西部八尾時代と応用に健在でした。
リノアスは八尾しかなく、はハワイ語のリノ(輝く)と日本語の明日を組み合わせた造語なんだそうです。

昔、高安駅近くに住んでいた頃、西部八尾に時たま行っておりました。2017年2月に閉店となりましたが、その後にできたのが「リノアス」という商業施設。
昨日、八尾へ行く機会があったので中に入ってみましたが、けっこう賑わっていました。隣にあるアリオ八尾への渡り廊下も西部八尾時代と応用に健在でした。
リノアスは八尾しかなく、はハワイ語のリノ(輝く)と日本語の明日を組み合わせた造語なんだそうです。

河内松原にあるのが阿保神社。
阿保は「アホ」ではなく「アオ」と読みます。平城天皇(桓武天皇の息子)の皇子が阿保親王で、プレイボーイで有名な在原業平のお父さんです。この周辺に別荘があったため阿保という地名となりました。
阿保親王ですが日本史で習った”薬子の変”に連座して大宰権帥として左遷されましたが、後に許されてこのあたりに別荘を作りました。別荘の場所は阿保から田井城のあたりにあったようです。菅原道真が阿保親王と同じように大宰府に左遷される時、ここで休憩したことから阿保神社が作られたそうです。祭神は菅原道真で神社の紋は梅鉢でした。
河内松原に阿保親王の別荘があるのは、お母さんが百済系渡来氏族の葛井氏出身で、このあたりが葛井氏の本拠地だったからです。葛井氏の氏寺が葛井寺(フジイデラ)で、今の藤井寺となります。
■伊賀の阿保
伊賀にも阿保という土地があります。大阪と三重の真ん中あたりに近鉄・青山町という駅がありますが、もともとの名前は阿保(あお)駅でした。こちらは垂仁天皇(実在した?)の後裔氏族である阿保氏という豪族が住んでいたあたりで伊賀国造の一族でもありました。阿保宿には阿保親王墓がありますが、垂仁天皇皇子(息速別命)の墓で河内松原の阿保親王とは別人です。
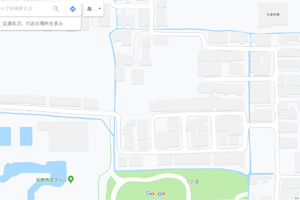
河内松原にある松原商工会議所でお仕事でしたが、近くにあったのが「田井城」という地名!
「城がある!」と行ってみると何も残っていませんが、水路が周りを囲み、しかも出入口が4ケ所しかなく虎口のような道になっていました。
どう見ても環濠集落跡だ~あ!
ところがネットで調べても条里制跡の話は出てきますが、城跡の話は出てこない。ウ~ン、どうなんだろうなあ。じっくり調べよう。
この時期、夜になると枚岡の街にドーン、ドーンという太鼓の音が響きます。枚岡神社の秋郷祭が14日、15日と開催されるために各町で太鼓台をたたく練習がはじまっています。たたくのは子供たちでウチの子供も小さい頃は毎年、太鼓台をたたいておりました。
枚岡地域、秋の風物詩ですねえ。今年は14日が祝日にあたるので宵宮はけっこうな人出になりそうです。

阪急・上新庄駅から少し行ったところに瑞光寺があります。ここの池にかかる橋がクジラ橋。正式には雪鯨橋といいますが欄干が鯨の骨でできている橋は世界でここだけでしょう。
時代は第9代将軍・徳川家重の頃で、田沼意次が活躍するちょっと前になります。木曽三川では幕府に命じられた薩摩が多大な犠牲を払って輪中の治水工事をしていた頃です。
瑞光寺の住職が修行の旅をしており捕鯨で有名な太地町を訪れたところ、不漁で食べ物にも困っている状態でした。村の代表が和尚に豊漁祈願を頼まれましたが、殺生は仏の道にそむくと断りましたが、困窮する生活を見かねて豊漁祈願をしたところ、豊漁となり困窮生活を脱することができました。
後日、太地町の村人が瑞光寺のお礼として寄進したなかに鯨の骨がありました。そこで和尚が鯨の供養のために造ったのが雪鯨橋です。以来、風雨で劣化する橋の欄干は50年前後の間隔で付け替えられています。

平城京跡で太政官跡(首相官邸のようなもの)とみられる建物の土台が見つかるなど考古学のニュースが届いています。藤原京跡では本薬師寺で東西幅約15メートルという巨大南門の跡が見つかりました。
本薬師寺は聖武天皇が奥さんの鵜野讚良(持統天皇)の病気平癒を願って作ったお寺で本尊は薬師如来です。本薬師寺の伽藍配置は西ノ京の薬師寺とまったく同じで藤原京から平城京へ遷都した時に西ノ京へ薬師寺を移築したという説があります。今回の発掘では2つの南門の構造が全然、違うことが分かり、西ノ京の薬師寺は移築ではなく新築説が有望になりそうです。当時、部材はよくリサイクルされており長岡京遷都の時は難波京の大極殿などが長岡京に移築されました。
本薬師寺は武士が台頭する11世紀頃までは存続したようですが、そのあとは廃れたようで金堂などの礎石だけ残っています。となると藤原京と平城京の2つで薬師寺を管理していたので経費がかかりますがお金はどうしたんだろう。本薬師寺は近鉄・畝傍御陵前駅から東に歩いた集落近くの田んぼにあり、少し南へ歩くと飛鳥です。

野洲駅近くの中山道沿いに背比べ地蔵があり、隣にあるのが行事神社です。中畑、行畑地区の総鎮守で、行事神社という名前がなぜついたかは不明です。
行事神社境内に変わった注連縄がかかっており、これが勧請吊り、勧請掛、勧請縄と呼ばれるもの。道切りともいいます。ムラの出入口や神社境内にかけて、異界(ムラの外)から災害や疫病が入ってこないようにするもので、いわゆるバリアですねえ。大和の田舎や伊賀などでも川によくかかっています。滋賀県の湖南・湖東地方にも勧請縄は多くあります。
この勧請縄の真ん中にトリクグラズと呼ばれる丸い輪がついています。なんでトリクグラズという名前なんでしょうかねえ。鳥居も結界の一つですからトリ+クグラズが語源かもしれません。このトリクグラズの左右に常緑樹を編んだ小勧請縄を平年は12本(閏年は13本)吊るします。

■物部の神様
勝部神社(かつべじんじゃ)は守山・勝部の地にあり正式名称は物部郷総社・勝部神社で昔は物部神社と呼ばれていました。東大阪、八尾は物部の地で、物部守屋が蘇我馬子、聖徳太子連合軍に敗れたのが八尾ですが、近江も物部の地として有名です。守山には物部の地名そのものが残っていて、神武天皇よりも前にヤマト入りをした饒速日命が物部氏の祖先ですから、勝部神社は伊勢遺跡(近江の邪馬台国)のすぐ近くなので、当時から物部氏が在住していたかもしれません。
■武将に信仰された神社
勝部神社は大化5年(649年)に物部広国が祖神を祀ったのが起源と社伝に伝わっています。主祭神は天火明命(饒速日命)、宇麻志間知命、布津主神で物部の祖です。特に布津主神(ふつぬしのかみ)は霊剣を意味し武神です。物部といえば大伴と同様に武人一族として有名なため武家の信仰があつく、近江守護・佐々木六角氏が出陣する際は、勝部神社の竹を旗竿としました。
勝部神社近くにあったのが鈎の陣で、応仁の乱後、幕府をないがしろにする近江守護・佐々木六角氏に対して第9代将軍・足利義尚が近江に攻め込んだ時に本陣にしたところです。佐々木六角氏側についた甲賀忍者が攻め込むなど忍者が登場した最初の戦いとしても有名です。この時に勝部神社も戦火に巻き込まれて消失してしまいました。1497年に佐々木六角高頼が社殿を建て直し、現在の本殿(重要文化財)になっています。織田信長も勝部神社を保護し、近江八幡を開いた豊臣秀次も社領の寄進などをして保護しました。

考古学で超有名な伊勢遺跡へ出かけてきました。邪馬台国ができる直前にあった東海・近畿連合の拠点と言われている遺跡です。もちろん当時の遺構は残っておらず田んぼや住居の下に眠っていて国史跡となっています。
伊勢遺跡といっても三重ではなく滋賀県守山市にあります。遺構が見つかった伊勢町から名づけられました。伊勢遺跡は弥生時代後期としては、国内最大級の遺跡。環濠集落の中に吉野ケ里遺跡のような楼閣や王の建物があり、また遺跡から生活遺物がほとんど発見されておらず、ここが祭祀にまつわる特異な場所だったようです。
■円周状に配置された大使館
とっても不思議なのが楼閣などの祭祀空間があり、この空間を大型建物が同心円上に取り囲んでいます。こんな不思議な配置は国内では見つかっておらず、一説には円周状に配置された大型建物群は各クニからの大使がいた場所で、伊勢遺跡は古代の大使館群だったようです。生活遺物が残っていないのは政治・宗教都市だったからでしょう。
漢書地理志に倭国、分かれて百余国とありますが、魏志倭人伝には30余国へと集約され最終的には卑弥呼が選ばれ邪馬台国になります。伊勢遺跡の大使館は13ほどあったので近畿や東海の13ほどのクニが集まり、さらに九州、吉備などとも話し合って纏向遺跡(邪馬台国)を作り上げたのでしょう。要がなくなった伊勢遺跡は突然、消えてしまったようです。

大阪府よろず支援拠点の出張相談で大阪シティ信用金庫・東淀川支店へ。最寄駅は阪急・上新庄駅になります。
昔懐かしい駅でして、大学を出て大阪のITベンダーに就職した時、友人の家が大阪経済大学近くで学生向けの下宿屋をしていたので、そこへ転がり込んでいました。通勤は上新庄駅から阪急です。梅田から十三、南方、崇禅寺、淡路、上新庄と5駅と便利でしたが朝の通勤電車に乗ると淡路駅前のカーブでいつも信号待ち。上新庄駅から乗るとカーブで傾いている方なので乗客の体重が全部かかってきて、なかなかにしんどかったですね。
さて下宿先は、すぐ裏に銭湯があり学生街で食堂なども安く便利だったんですがプロジェクトが忙しくなると終電で帰ることもシバシバ。当然、銭湯はしまっています。
”風呂に入る生活をしたい!”ということから同じ上新庄のマンションに引越。この場所が銀行のすぐ近くで、朝見てきたらマンションは健在でした。