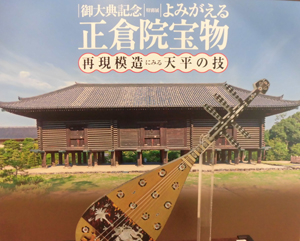大阪府よろず支援拠点の出張相談で堺へ。行きは南海で行きましたが、帰りは久しぶりに阪堺線に乗りました。

阪堺線は大阪(天王寺or恵美須町)と浜寺駅前を結ぶチンチン電車で、専用軌道も走りますが一般道路を車と一緒に走ります。大阪のチンチン電車は今は阪堺線だけになりました。
堺の市街地を抜け、大和川を渡り天下茶屋からミナミを目指します。住吉神社近くの住吉駅で天王寺へ向かう上町線と恵美須町に向かう堺線に分岐します。昔は交差になっていて住吉大社駅があったのですが、なくなってしまいました。
そうそう阪堺線を舞台にした「阪堺電車177号の追憶」(ハヤカワ文庫)という小説が出ていました。「阪急電車 片道15分の奇跡」のように映画化されないかなあ。