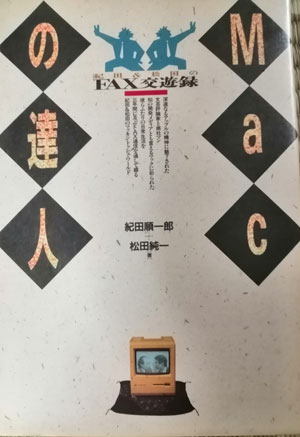隠岐のスーパーマーケット事情
■島前と島後
隠岐諸島は島後(どうご)と島前(どうぜん)から成り立っています。都にちかいほうが島前になりますが、越前、越後と同じです。昔は道後、道前だったんですが江戸時代の役人が「島」と書き間違えて以来、島後になったとか、隠岐の人に聞きましたが、ほんまかいな。でも島と書いて確かに「どう」とは読みませんなあ。
■スーパーマーケット
道後は平野が少なく空港やフェリー乗場などがある西郷湾のあたりが中心地になります。道後にあるスーパーマーケットは2軒だけですが、この平野にあります。現在、ショッピングセンターひまり(Himari)が改装中で、なんでも平の前ショッピングモールができるそうです。もう一軒のスーパーマーケット「ショッピングプラザ サンテラス」が車で5分ぐらいのところにあり、人口減のところ、なかなか熾烈な戦いですね。