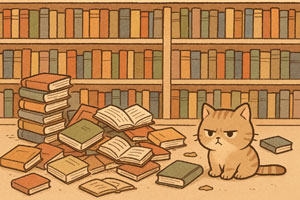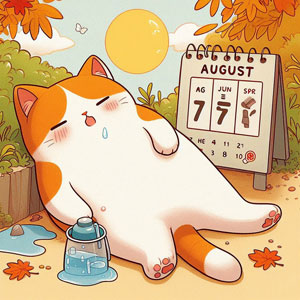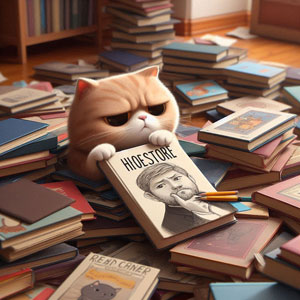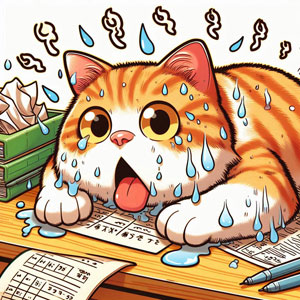北勢地域にあるCTY(ケーブルネット)のインスタを見ていると関ケ原戦跡踏破隊の話題がのっていました。
関ケ原戦跡踏破隊は郷土の先人の偉業を体験する青少年教育プログラムで、鹿児島県日置市の小・中学生が中心になっています。たどるのは島津軍の退路です。
■島津の退き口
関ヶ原の戦いで結果的に戦場に取り残される形となった島津軍が、後ろへ下がらず家康軍の敵中突破をして退却します。島津の退き口(しまづののきぐち)として有名ですが、薩摩に帰り着くまで辛酸な撤退戦になりました。島津軍は伊勢街道を下り近江、奈良を経由して堺へたどりつきます。
この島津軍の退却コースを2日間で学ぶコースで、今年でなんと66回目で、さすがは郷中教育の薩摩です。