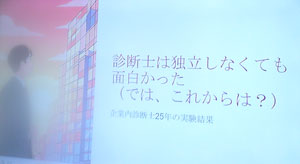鯏は「うぐい」「あさり」とよむそうで、なかなかの難読地名ですね。愛知県弥富市鯏浦町にある城跡ですが、遺構は残っておらず現在は薬師寺になっています。織田信長の重要な収入源が津島でしたが、その南側をおさえていたのが服部党で頭領だったのが服部友貞です。桶狭間の戦いでは今川義元に組していました。
この服部党を牽制するために1565年(永禄8年)に織田信長が築いたのが鯏浦城です。城主は信長の弟である織田信興です。今は住宅地ですが城の横が海岸線だったようで、大楠が残っており、樹齢600年以上といわれるので信長時代からあった楠になります。この楠に秀吉が船をつないだと伝わっています。