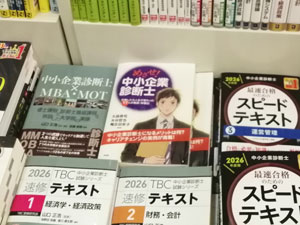箸墓から上ツ道を北上するとJR纏向駅に着きます。駅のすぐ隣にある纏向遺跡を久しぶりに見てきました。邪馬台国・畿内説の最有力候補地で、2011年に大型建物跡が見つかってからは特に注目されるようになりました。
纏向遺跡は3世紀初めに突然現れた集落です。関東から九州にいたる土器が発見され、全国から人が集まっていたようですが、生活用具の出土が少なく政治・宗教都市だったようです。滋賀県・守山に伊勢遺跡があって中央の建物を中心に環状に建物群が並び、各地域の代表者が集まって協議した場所のようですが、ここで話し合って山に囲まれた纏向に都市を作ろうと決まったかもしれません。
纏向遺跡では寒いので車で待機していたボランティアの説明員が近づいてきて10分コース、30分コースで説明できますが、ということで10分コースでお願いしました。内容的には知っている内容だったのですが、「古墳時代の歴史」(講談社現代新書)読みましたかという話で盛り上がっていました。