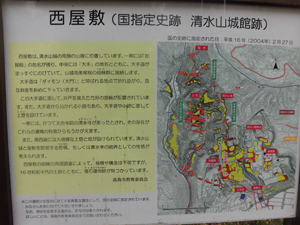長法寺は戦国時代頃に廃絶となったようですが、寺域の入口に山城が造られています。それが長法寺城。高島方面から山道をひたすら登った先にあります。もともとは坊があったようで急遽、山城に造り替えたようです。3つの郭が連格式でつながり、入口は堀切を進む形になっています。寺側の入口は食い違い虎口になっていました。

長法寺は石垣の寺ですが、長法寺城は土の城で、急ごしらえで造ったのでしょうね。打下城方面からの攻撃には特に備えていないので、一帯で運用していたとすると織田信長との戦いに巻き込まれていたのかしれません。