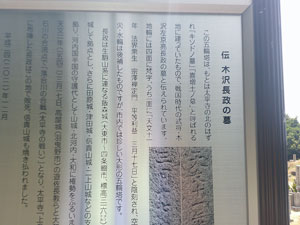京橋でお仕事だったので帰りは久しぶりにOBP(大阪ビジネスパーク)へ。大阪砲兵工廠があったところで小松左京の「日本アパッチ族」の舞台となったところです。今は再開発され超高層ビル群と公園で構成されています。TWIN21ビルのすぐ横にあるのがIMPビルで上に貸し会議室があり、20年ほど前、ITコーディネータのケースケース会場として使っていたので、よく来ていました。懐かしいな~。

IMPビルの隣には読売テレビのビルができていてコナンの銅像もありました。そうそう団扇をもった女性がたくさんいて、大阪城ホールでキンプリのコンサートだったんですねえ。その後、ITコーディネータの研修会場は梅田スカイビルに移り、最後は松屋町のUHA味覚糖ビルとなりました。