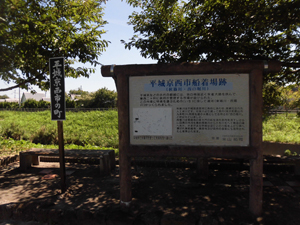大安寺境内で見つけたのが推古天皇社。
祭神はもちろん豊御食炊屋姫尊(とよみけかしきやひめのみこと)つまり推古天皇です。新しく建てた神社かなと思うと、どうも違うようで昔の大安寺の伽藍を描いた図に東側に推古天皇と書かれ西側には聖徳太子と神社らしきものが書かれています。いつからあるのかなあ。大安寺が飛鳥から移転した時に神社もついてきたのかもしれません。
■日本に2つだけ?
そういうば大和郡山の額田部を歩いていた時にも推古神社を見つけました。推古天皇は額田部皇女(ぬかたべのひめみこ)とも呼ばれていたので額田部郷と関係があったのでしょうか。大安寺はもともと聖徳太子が平群郡の額田部に創建した修行道場なんで額田部というと平群郡で、大和郡山の額田部からは山を一つへだてています。
こういう時に便利なのが法人番号検索サイト。「推古」で検索すると該当するのは推古神社だけ。とすると推古天皇に関する神社は日本全国にこの2つだけしかないのかなあ。