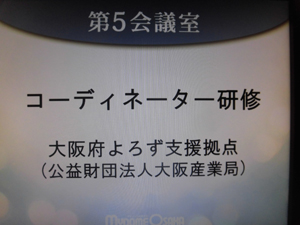皆さま、お待ちかねの普賢寺谷・城館群シリーズ。今回は小田垣内遺跡です
垣内という地名がついていますので、かって城がありました。他にも内本町のように内がついていると城内を指す場合が多いです。
京奈和自動車道のすぐ横の山の中にあります。隣には同志社大学多々羅キャンパスがあります。近くまで小道があり、ここから郭内に入れるが楽ですね。小田垣内遺跡はけっこう古い時代から使われていたようで室町時代の石仏が土塁の中から見つかっています。
高い土塁と堀切などが見事に残っていました。けっこう大きな郭跡ですので、いろいろな館が建っていたようです。谷の反対側に大西館がありますので、大西関係者の城だったかもしれません。