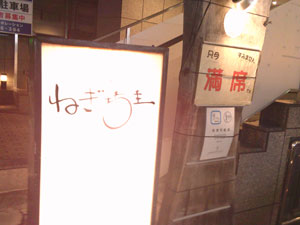日本最古の神社といえば大神神社、花の窟神社の名前があがりますが、もう一つあります。それが大和(おおやまと)神社で上ツ道沿いにあります。創建は第10代天皇が崇神天皇になります。
■大神神社誕生
崇神天皇は「はつくにしらすすめらみこと」とも呼ばれており実在した最初の天皇と考えられています。崇神天皇の時代に疫病が流行し、三輪山の大物主大神(オオモノヌシノオオカミ)の怒りとわかり、神の子孫となる大田田根子(オオタタネコ)に祀らせたところ鎮まって、これが大神神社となります。
崇神天皇には、もう一つ神社にまつわる話があり宮殿で天照大神と倭大国魂神を祀っていたのですが、世の中が乱れるのは両神の勢いのためという、よう分からん理由で外へ出されることになります。なにか日本書紀には記載できないことがあったんでしょうね。
■伊勢神宮
天照大神を皇女豊鋤入姫命が笠縫邑に祀ります。これが山の辺の道沿いにある檜原神社で、後に倭姫命が各地を巡り、最終的に伊勢神宮が天照大神の鎮座地になりました。
■戦艦大和
倭大国魂神は皇女渟名城入姫に託しましたが、こちらはうまくいきませんでした。紆余曲折があり、大和神社になります。倭大国魂神は大和の国全体を守る神様で、航海安全の守護神ともされましたので、遣唐使が渡航前に参拝しました。戦艦大和の艦内神社には倭大国魂神の分霊が祭られました。