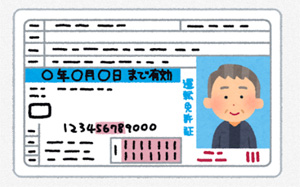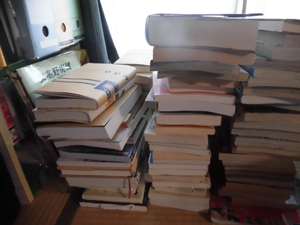毎年、読んだ本を記録していますが2022年は117冊でした。例年、100冊ぐらいが通常で、読むスピードはそれほど変わらないため要因は本の分量が20%ほど減ったということです。だいたい本のポイント数がだんだん大きくなるのに枚数が同じだと字数が減るしかないですからね。特に新書で顕著です。
ちなみに年越しをしながら読んでいる本は「商社マン、エルサルバドル大使になる」(集英社新書)、「激闘!賤ケ岳 羽柴軍VS.柴田軍」(洋泉歴史新書)、「図説 六角氏と観音寺城」(戎光祥出版)の3冊で、我ながら偏っていますねえ。
年間100冊読んでも50年間で5000冊しか読めないんですなあ。これで読んだ内容を覚えていたら大したものなんですが、大体、内容を忘れています(笑)。