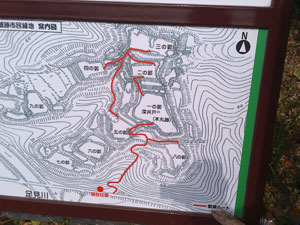四日市商工会議所で仕事なんで駅近くの浜田城へ寄ってきました。
主郭跡は鵜森神社になっていて郭の周りは鵜の森公園になっています。四日市駅のすぐそばですが神社を囲む三方の土塁がよく残っています。文明2年(1470年)、田原忠秀によって浜田城が築かれたと伝わっています。田原忠秀は上野国佐位郡赤堀を本貫とする赤堀氏の一族で上野国から伊勢へ移り、浜田城を築きました。東海道や市場の整備も行い、四日市という地名はこの頃にできたそうです。
3代・田原元綱の時、織田信長の伊勢攻めで滝川一益に攻められ落城します。城はそのまま残っていたようで小牧・長久手の戦いの時、織田信雄方の滝川雄利が松ヶ島城を開城した後、浜田城に移って籠城したと記録されています。