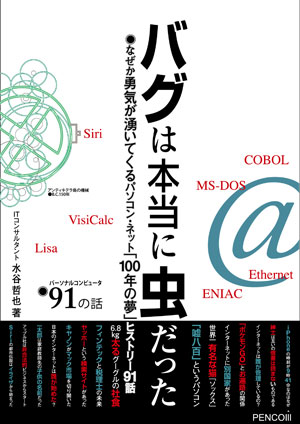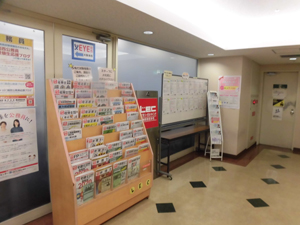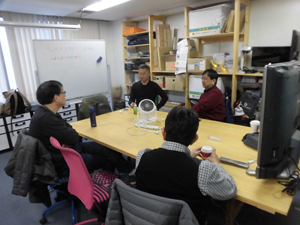見た目は単なる丘ですが、奈良の大仏よりも大きな大仏があったところです。
造ったのは秀吉で三好三人衆と松永久秀の戦いで奈良の大仏が焼けて破損したこともあり、奈良より大きい6丈3尺(約19m)の大仏と大仏殿を造りました。五条大橋を六条坊門に移して、大仏への参詣道とし、これが今も残る正面通りです。
ところが翌年に起きた慶長伏見地震で大仏が倒壊してしまい、秀吉は「自らの身をも守れないのか」と大仏に怒り心頭。大仏を再建することなく秀吉が亡くなってから秀頼が大仏を完成させます。大坂の陣の後も大仏は残っていましたが、寛文2(1662)年の地震で大破してしまいます。