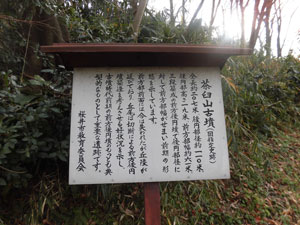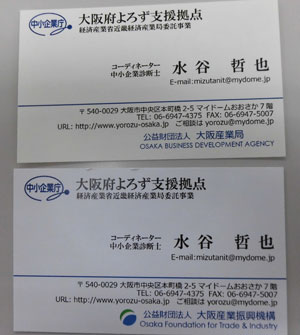今は昔、Fchikenというフォーラムありけり。パソコン通信なる面妖なものに取りつかれし衆生が集まる場所なり。
ということで大昔にNifty-Serveという富士通と日商岩井がやっていたパソコン通信があり、そのなかにFchiken(知的生産の技術)フォーラムやFbman(ビジネスマン)フォーラムなんてものがありました。
そんなパソコン通信の時代は、はるかかなたとなりながら、折に触れて残党が集まっています。本日、東京から珍しくくるメンバーがいたため残党が集まったのが日本一短い商店街「肥後橋商店街」にある福助。
ここも昔からオフ会などで使っているお店で、おばちゃんもあいかわらず元気ですねえ。なんやかかんやか3時間ほど飲んで帰ってきました。あいかわらずリーズナブルな価格です。