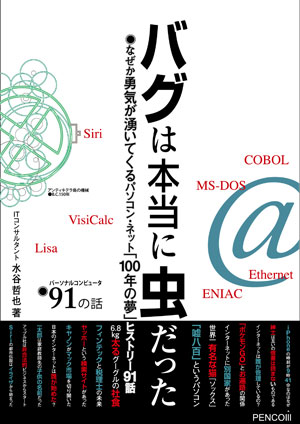昨夜は知研関西セミナー。「あなたの知らないクラウドファンディングの世界」教育のチャンスを守る。カンボジアの子ども達に通学用自転車を!というタイトルで安田コンサルティング代表の安田さんにお話しいただきました。
安田さんは2年連続でクラウドファンディングReadyForを活用し、2018年は目標額120万円に対して146万円の支援金を獲得して、先日カンボジアで自転車を子供たちに158台プレゼントし帰国したばかりです。
クラウドファンディングで2回プロジェクトを達成するのは至難の業で
・支援金の波(法則があります)と波にあわせた施策
・事務局とどんなやりとりをするのか
・訪問者数と支援者数との相関
・手数料はとるが、それ以上のサポートをReadyForがするワケ
など、クラウドファンディングを実際に行う上でのいろいろなノウハウを教えていただきました。
カンボジアについても知らないことばかりで
■世界遺産アンコールワット
入場料が7千円ほどと高く、貧しいカンボジア支援になればと思っている観光客が多いのですが、お金はベトナムに流れます。
■子供たちが将来つきたい職業
80%が先生、医者、看護士で、農村から出たことがなく身近で見る大人の職業がこの3つだけ。両親はほぼ農家ですが土地は中国人がもっているため小作農となり生活は貧しく1年間の食糧確保ができない家庭が多くあります。
通学用自転車は3年持てばよく日本の中古自転車が現地にたくさん輸入されており現地で購入してプレゼントしています。自転車のカゴには支援者の名前や会社名が入ります。また悪路のため修理キットがセットです。
日本と同じで女の子が修理は難しいため学校に自転車クラブを作ります。生徒には一人ぐらい自転車屋の息子がいて家業の手伝いをしており、安田さんがささやきます。「今なら自転車クラブの初代部長になれるぞ。女の子が困っているのを助けたら3人に1人くらいは、ほれてくれるかもしれないぞ」これでイチコロだそうです(笑)。自転車クラブではプレゼント以外の自転車のメンテナンスも行い。技術を学んで自転車屋での独立を考える生徒も参加しています。各学校で設立された自転車クラブへのパーツ補給が課題になっています。