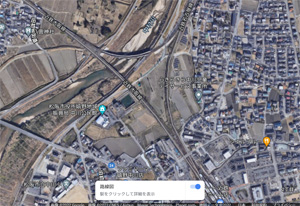廃線跡をゆく
山陰本線の廃線跡に作られた嵯峨野トロッコ列車です。チケットがとれたので亀岡から嵐山まで乗ってきました。保津川沿いを進んでいきますが、ちょうど保津川下りをしているのが見られます。保津川下りの船は嵐山でトラックに乗せられ、亀岡まで運ばれるところを見かけます。
保津川は奈良時代から丹後の材木を運ぶために材木を筏にして流していました。江戸時代に角倉了以が保津川を開削して船が通れるようにします。最初に船に乗って保津川下りを楽しんだのが角倉素庵(角倉了以の息子)です。
嵯峨野トロッコ列車、秋だとライトアップや紅葉が楽しめますがチケットをとるのが大変ですね。