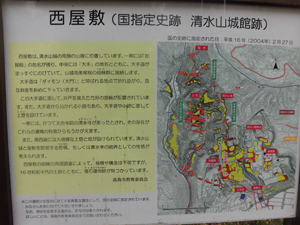織田信長より先に天下をとった三好長慶ですが後継者の息子に先立たれるなど晩年は不遇でした。

三好長慶は永禄7年(1564年)に42歳で亡くなりました。この年、美濃では斎藤龍興を諫めるため竹中半兵衛が稲葉山城を乗っ取り斎藤龍興を半年ほど追い出す事件がありました。織田信長は桶狭間の戦いに勝利し、徳川家康と同盟することで東側の脅威をなくし、本格的に美濃攻めをしていた頃です。
■御体塚
三好長慶は飯森山城で亡くなり、遺骸は郭に塚を作って仮埋葬されました。これが御体塚ですが、郭はハイキングコースから微妙にはずれていますので誰もおりません(笑)。その後、八尾にある真観寺に墓は移されます。
■三好義継が家督を継ぐ
三好長慶の後は甥が継ぐことになり、これが三好義継です。松永久秀や三好三人衆がバックアップしますが、家督を継いだのが15歳ぐらいですので内紛が発生。しかも織田信長の上洛もあって、三好家はしっちゃかめっちゃかになります。最後は追放された足利義昭を若江城で匿ったため織田軍に攻められて25歳で討死しました。この三好義継の墓も八尾の真観寺にあります。