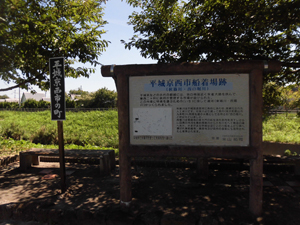近鉄・桜井駅からまっすぐ南へ行くと谷という土地があり、ここの丘陵上に若櫻神社があります。戦国時代には城が造られ土塁跡がいまも残っています。

仁徳天皇の息子である第17代、履中天皇が皇后と磐余の市磯池で遊宴中に、桜の花が盃に落ちたことを機に宮を磐余稚櫻宮と名づけます。この谷にある若櫻神社ではないかと言われていましたが磐余池が発掘で見つかったことから、池ノ内の若櫻神社が濃厚です。
池ノ内の若櫻神社は磐余池跡から東に行った小高い丘の上にあります。階段を登ったところに社殿がありますが、大きな削平地が確保されており、城を造るには絶好の場所ですね。当時の大和朝廷はまだまだ安定していなかったので丘の上を宮にしたのかもしれません。磐余の市磯池は若櫻神社の東側にあった模様で、現在は田園地帯になっています。