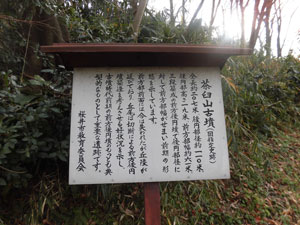平群町のマスコット、長屋王ともう一人は島 左近です。
戦国時代、島氏の本拠は平群町で平城の西宮城と山城の椿井城を本拠地にしていました。島左近は筒井順慶に仕え重臣になっていましたが、順慶が病に倒れてしまい跡を継いだ順慶の甥・筒井定次とは意見が合わず、筒井家を辞することになります。島左近は天下の名将ですから、多くの誘いがありました。そんななか、新しく主君になったのが石田三成です。自分の禄高が4万石なのにそのうちの半分の2万石を与えるという破格の条件を呈示、意気に感じたのか石田三成に仕えることになります。
「三成に過ぎたるものが2つあり。島の左近に佐和山の城」と言われるようになります。関ヶ原の戦いでは本戦の前に行われた杭瀬川の戦いでは兵500を率いて東軍の中村一栄・有馬豊氏両隊に戦いを挑み、明石全登(宇喜多秀家の家臣だった)隊と共に勝利して、士気をあげました。関ヶ原合戦でも大いに戦い、徳川方は「誠に身の毛も立ちて汗の出るなり」と記録しています。