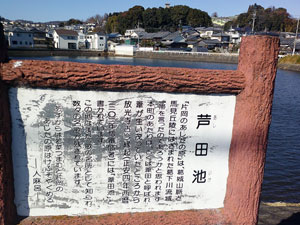国道308号は大阪の難波から奈良(平城京)を結ぶ国道ですが、酷道という名前がついています。特に暗峠を超えるのは大変で車は4駆でないとまず無理です。暗峠を超え進んでいくと矢田丘陵上に追分があります。暗越奈良街道を、そのまままっすぐ進むと奈良に至ります。遠くに若草山が見えています。奈良時代から江戸時代にかけて、この道がメインルートで、多くの旅人が行き来しましたが、今は時たま車が通るぐらいです。
追分を右に曲がると大和郡山へと向かいます。追分には本陣・村井家住宅が残っていて江戸時代は大和郡山藩主の休憩に使われました。奈良に入ると大和郡山領でしたので暗峠に残る石畳は大和郡山藩が整備し、暗越奈良街道の管理もしていました。