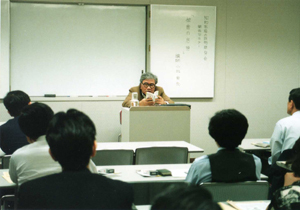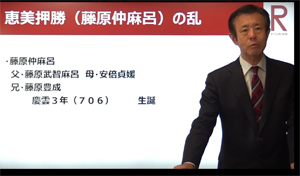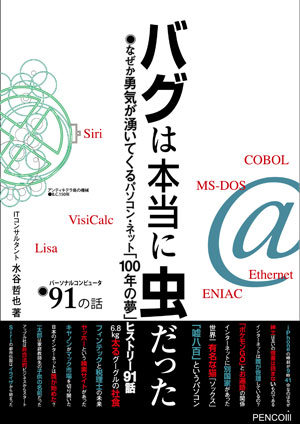永原城
永原城写真の水田が堀跡で本丸は右側の竹藪の中にあります。
■将軍専用宿泊施設
野洲にある朝鮮人街道(中山道の脇街道で織田信長が安土城を通らすために整備、江戸時代は朝鮮通信使が通る道)から琵琶湖側に少し入ったところに永原御殿跡(永原城)があります。関ヶ原の戦いの勝利後、家康が佐和山から安土、永原と朝鮮人街道を凱旋して上洛したことから、この道が吉礼の道となりました。家康の上洛用に本丸御殿を関ヶ原の翌年(1601年)に設けます。
もともと秀吉が家康に野洲を在京賄料(出張経費)として与えていました。やがて江戸幕藩体制となり、将軍専用の宿泊・休憩所として秀忠、家光時代に御茶屋御殿が整備されます。近江にあった将軍専用宿泊施設が永原御殿(野洲市)、伊庭御殿(東近江市)、水口御殿(水口城跡・甲賀市)、 柏原御殿(米原市)の4つです。
■御殿といいながら戦国の土の城
永原御殿という名前ですが、戦国時代に作られたのですから土塁と堀に囲まれた土の城で櫓が建ち並んだ平城でした。本丸内に御殿が建てられ、徳川家光の上洛では、本丸のほか、二の丸や三の丸が設けられます。現在の永原御殿跡は、竹藪や民家・水田などとなっています。
本丸跡に入って土塁を眺めてきましたが、この時期はまだまだ藪蚊だらけで、這う這うの体で退散してきました。城巡りにはもっと冷えないといけませんなあ。
■信長公記に出てくる永原城はここではなかった
佐々木六角氏の重臣だった永原氏によって築かれた永原城があり、信長公記に出てきます。信長の近江侵攻で敗れ、信長の重臣である佐久間信盛が城に入りました。この永原御殿が永原城跡ではないかと言われていました。
発掘調査の結果、どうも永原御殿から700mほど行った祇王小学校にあったようです。信長公記に「永原の佐久間与六郎所」という言葉があり、与六郎が祇王小学校あたりの小字でした。